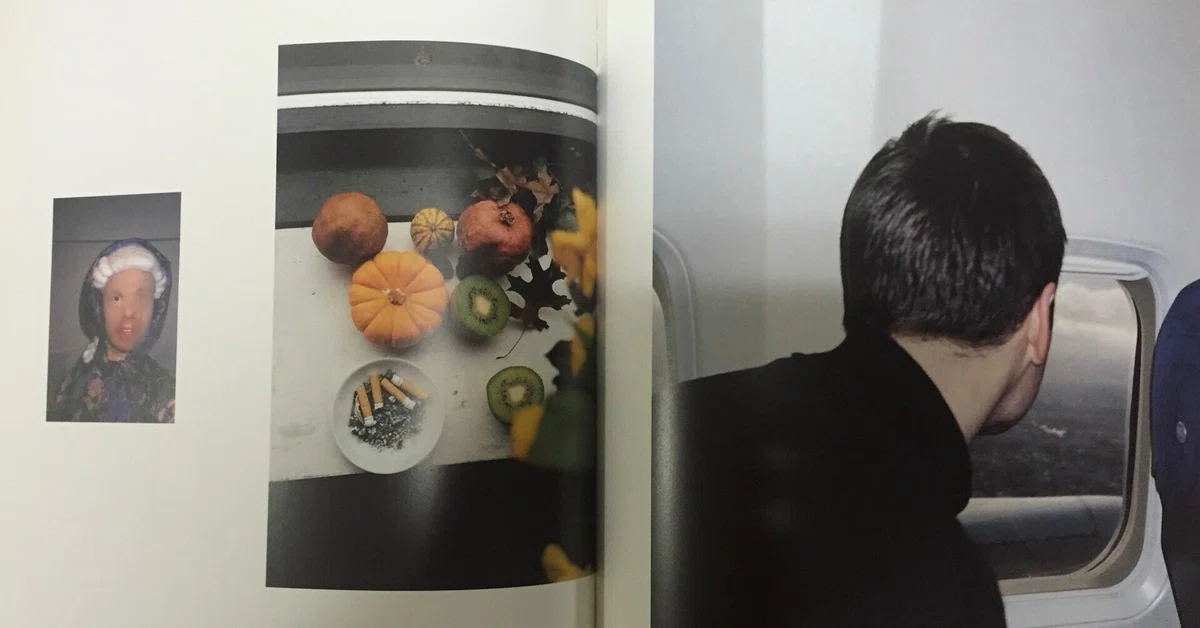-

インターネットだけで生計を立てることのリスクについて考えてみた
インターネットを活用して生計を立てる人が増えて、かなりの時間が経ちました。最初はブログから始まり、今ではYouTube、Instagram、TikTokといったプラットフォームの隆盛がそれを後押ししています。
僕もまた、収入の大部分をインターネットから得ています。SNSの収益や広告収入だけでなく、写真・動画撮影やライティングといったクライアントワークでさえ、ネットが無ければ成立しにくいのが現状です。
今回は、特にプラットフォーム依存によるインターネットビジネスのリスクについて考えてみたいと思います。この話は、すでにフリーランスとしてネットで仕事をしている人だけでなく、会社員や、これから何らかのプラットフォームで収益を上げようとしている人にも役立つはずです。
リスクを考えるきっかけになった出来事が二つあります。
一つ目は、AIの急速な進化によるホワイトカラーの仕事の変化です。事務作業やデスクワークだけでなく、コンサルティングやクリエイティブ業のような「人間ならでは」と思われていた仕事までも、AIに代替される可能性が出てきています。目に見えない部分で、すでにその波は広がっています。
二つ目は、アメリカの政治情勢によるプラットフォーム規制の影響です。今年、TikTokが一夜にしてアメリカで利用できなくなった出来事は、1億7000万人ものユーザーに影響を与えました。最終的にはアプリは復帰しましたが、TikTokを“仕事”にしていたユーザーたちは、早々に中国のアプリ「小紅書(Rednote)」に移行を始めていました。
イーロン・マスクによるTwitterの買収も記憶に新しいですね。突然の買収、社名変更、オフィス閉鎖や大規模な人員削減、これらは、プラットフォームが一夜にして大きく変わる現実を示しています。
こうした状況から、今普通に使えているプラットフォームが、ある日突然使えなくなる可能性は、決して低くないと感じています。そして、YouTubeやInstagramといった米国企業に収益の大部分を依存することは、実は一つの会社に勤めていることと同じくらいのリスクをはらんでいるのかもしれません。
そこで、インターネットビジネスのリスクと、その対策について考えます。
リスク
1、規制強化
政治的な情勢や国際関係の変化により、プラットフォームやインターネットの利用に規制がかかる可能性があります。特に広告収益モデルやスポンサーシップにも影響が及ぶことがあります。 -
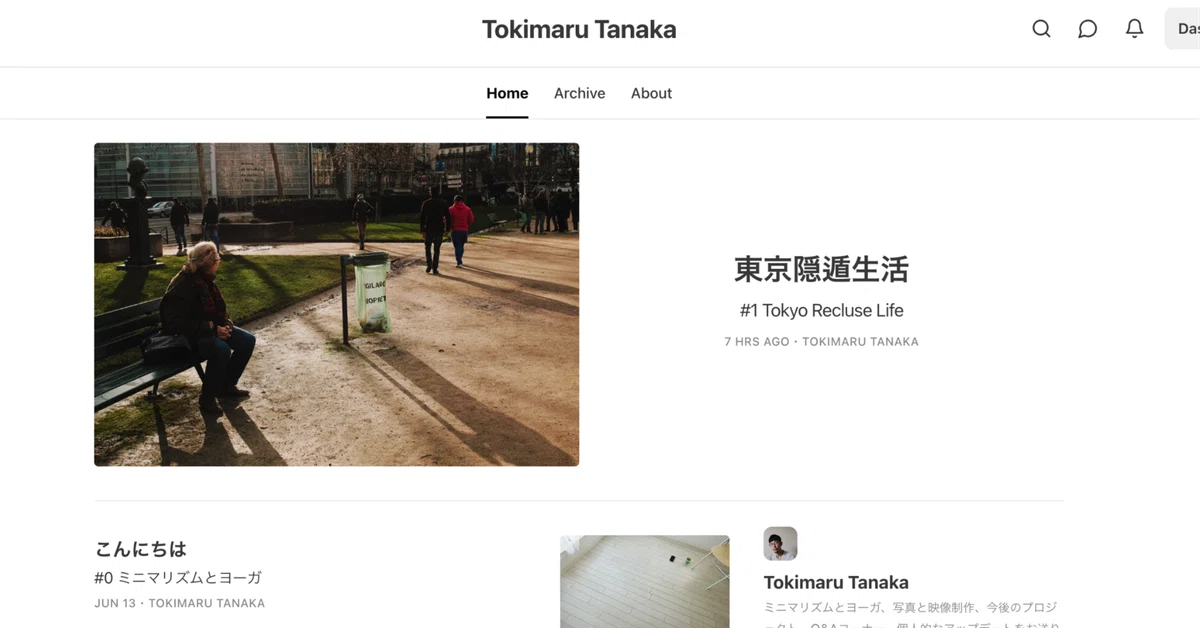
なぜSubstackか?noteやワードプレスとの違い
先週からSubstackでニュースレターの配信を再開しました。いわゆるメルマガです。初回から想像より多くの方に購読して頂き、驚きと嬉しさが入り混じっています。ありがとうございます。
https://tokimarutanaka.substack.com
Substackはメールマガジンの配信スタンドでありながら、ブログのようにWebサイトとして読むこともでき、最近はPodcastが配信できたり、ユーザー同士ではTwitter的なフィードのようなものを使いコミュニケーションができるようになっているプラットフォームです。誰かの言葉を引用して自分の記事内に置くことを「スタックする」と表現しています。
noteやワードプレスとの一番の違いは、メールボックスに直接記事が届くということです。もちろん、ワードプレスでもメルマガのような機能を実装することはできます。しかし自分でカスタマイズする必要があります。対して、Substackは本来その仕様になっていますので、何も設定せずともメルマガ配信がスタートできます。
今回はブログで文章を書いている人や、これからブログやnoteを書き始めたいけれど、どのプラットフォームが良いか迷っている人に向けて、Substackとnoteとワードプレスブログのそれぞれの違いや特徴、利点と弱点などを紹介します。情報発信をしたいけれど、何から手を着けてよいかわからない人、これから何かを書きたい人へのヒントや動機づけになれば幸いです。
目次
- 一番簡単なプラットフォーム
- WordPress
- Substack
- フィードとストックを考える
- 収益化の原則と本質
- コンテンツ継続のコツ
- なぜSubstackなのか
一番簡単なプラットフォーム
まず結論からいきます。Substack、note、ワードプレスブログの中だと、一番手軽に始められるのはnoteです。
アカウントを作って、右側の書くボタンを押すことで、すぐに執筆を始められます。合わせて、プロフィールやホーム画面の設定をしてみてください。あとは書いていくにつれてnoteが、キーポイントに達した時に自動的に通知して応援してくれます。どのようにプラットフォームを伸ばしていくか、ある程度自動的にサジェストしてくれるわけです。良く出来ています。
私は2016年からぽつぽつと投稿し始めて、今年で8年、書いた記事は442本。ブログは学生の頃から20年ほど書いてきたので、開始に問題は全くありませんでした。開始当初はもっと機能も簡素で上場前で小規模だったため、参入のタイミングとしてはアーリーな部類に入ると思います。少しでも他のブログサービスで書いたことがある人なら、エディタもなかなか使いやすく、楽だと感じるはずです。
フォローしていなくても記事を読んだり買ったりできるので、収益効果は高いですが、ストック型プラットフォームにしてはレコメンドのアルゴリズムがやや弱い印象。Twitterのようなひとことの「つぶやき」や、音声や、動画も投稿はできるのですが、設計的には書く専門の印象が強く、それが可読性の高いデザインに現れています。つぶやきはXが強いし、音声はPodcastが圧倒的に強い。だからnoteでは書くことに集中したほうが良さそうです。もちろん様々なコンテンツを複合的に上手く展開している人も稀にいます。
ひと記事あたりで販売ができるのも特徴です。その他には、マガジンという月額販売の方法や、メンバーシップを運営することも可能です。
販売時の事務手数料とプラットフォーム手数料が下記のように徴収されます。
事務手数料
コンテンツの決済手段により以下の料率を乗じた額を差し引きます。
クリエイターご自身が登録されている決済手段ではなく、購読者の決済手段によります。
クレジットカード決済 :売上金額の5%
携帯キャリア決済 :売上金額の15%
PayPay決済 :売上金額の7%
ポイントでの決済 :売上金額の10%
プラットフォーム利用料
売上金額から事務手数料を引いた金額に以下の料率を乗じた額を差し引きます。
有料記事、有料マガジン、サポート、メンバーシップ:10%
定期購読マガジン:20%note:コンテンツを販売する際に引かれる手数料
これに対して高いと文句を言っている人もいますが、プラットフォームマージンとしては通常の範囲だと思います。これを割るとビジネスとして成立させるには厳しいです。上場しちゃってるという手前、四半期ごとに昨年の売上を超えないといけないわけですから、厳しいんですよね。この資本主義。
WordPress
-

1枚のクレジットカードで生きる
クレジットカードは1枚しか持っていない。正確には2枚だがそれはクレジットタイプのデビットカードなのでほぼ使わない。メインのクレカ1枚で暮らしている。
家計管理には人それぞれの方法があり、選択肢も無限なので、悩み始めたら止まらないという状況になりがちだ。そこでミニマリスト思考が少しは役に立つかもしれない。
あらゆる管理の手間を最小化することはミニマリズムの基本である。クレカや銀行口座も1つにすることで、管理はシンプルになり、キャッシュフローは明確になり、不正利用にも気づきやすくなり、使い過ぎもわかるので、お金が貯まるようになる。クレカだけでなく、家計簿や収益計算書などの財務管理はシンプルであればあるほどいい。特に個人の場合は。
今回はクレカの話しに的を絞りたい。
年末が近づいてきて、様々な整理やまとめをする中で、クレカを変えようと思った。これまで使っていたカードは2年くらい使用していて、その前も2年、その前は6年、という感じで定期的に変えたい時期がやってくるが、最近はそのサイクルが早くなっている。企業の入会キャンペーンが手厚くなっていて、変える方が得をする、という状況にさえなっていると思う。(そのテクニックは後述する)
電子決済とクレカの導入は早くて、初めて就職をした頃から基本はカード生活で、20代後半の頃には完全にキャッシュレスライフに移行した。20代前半の頃はリボ払いの罠にハマり、30万ほどの残高、つまり借金を抱える時期が続いたこともあった。
財務状況が好転したのは28歳くらいの時で、ミニマリズムに出会った頃と重なる。
全ての借金やローンを完済して、ポイント効率の良いカードに変えて、それ以降は同時に2枚以上のクレカを持つことはなく、いつも1枚だけをコアに使い倒すというスタイルになった。それは現在でも続いている。
これまでのクレカ履歴を時系列に記しながら、使用感を振り返ってみたい。
-

楽天経済圏、もう不要。私が抜けた理由と新しい最適解
かつては楽天経済圏をフル活用していた。楽天カードをメインの決済手段にし、楽天市場で買い物をし、楽天トラベルで旅行を手配し、楽天ポイントを貯め、そのポイントでスマホ代の全てをまかなう。そんな生活をしていた時期がある。
確かに楽天経済圏にどっぷり浸かることで、ポイントの還元率は高くなり、無駄なくお得に生活できる感覚はあった。しかし、それが本当に「最適解」だったのか、時間が経つにつれ疑問を持つようになった。特に、近年のGoogleの進化や、価格比較サイトやOTAの発展により、楽天経済圏が必ずしも最安ではなくなってきたのだ。
今では、私は楽天経済圏をほとんど利用していない。楽天だけでなく〇〇経済圏というものすら手放している。唯一使っているのは「楽天モバイル」のみ。これは単純に業界内で最安かつ無制限のため、他に選択肢がないからだ。しかし、それ以外の楽天サービスについては、すでに利用価値がなくなってしまっている。
では、なぜ楽天経済圏を抜けたのか。その理由を詳しく解説していこう。
楽天経済圏が時代遅れになった理由
-

仕事ではなく習慣を作ること
何かを変えたい、今の現状から抜け出したいと考えたことはないだろうか?
目の前にある日常に不満を持ちながらも、それに縛られ続ける。頭では「変わらなきゃ」と思っているのに、行動が追いつかない。その繰り返しが続くと、いつの間にか「変えたい」という感情が「まあ仕方ないか」にすり替わってしまう。気づけば、何年も同じ場所に立ち尽くしている。現状を変えたいと思うなら、どうすればいいのか?
これは、誰にとってもシンプルで、そして難しい問いだ。しかし、確実に言えることがある。
自由は、突然訪れるものではなく、自分の手で縮めていくもの。あるいは積み重ねた日常と習慣の間に立ち現れてくるものだと思う。
目次
- 自分を辞められない理由から解放する
- 謎めく存在、選択肢の拡大
- 仕事を習慣に変えることで自由になる
- 自由のゲーミフィケーション
自分を辞められない理由から解放する
変化を阻む最大の要因は、辞められない理由付けにある。
仕事、生活、環境、お金など。人それぞれの辞められない事情があり。いつも言い訳を作り、先延ばしにしている。しかし、それらは本当に「絶対に辞められない」のだろうか?例えば、今の仕事に不満を感じながらも続けている人は多い。理由を尋ねると、「辞めたら生活が成り立たない」「今の収入を捨てるのは怖い」「今の仕事をやめた後に、どうやって生きていくのかわからない」という答えが返ってくる。
だが、もし本気で自由を求めるなら、こう考えるべきだ。
-

エクストリームミニマリストの条件
エクストリームミニマリストの条件とは何だろうか。
持ち物が50個以下の人?ネスカフェを飲んでいる人?それとも仕事も手放している人?
どれも当てはまりそうだけど、仕事も手放していることは持ち物を減らすことに役立つ。仕事が無いから持ち物が少ないのか、それとも持ち物が無いから仕事ができないのか。
僕の師匠とも先輩とも言える米国のミニマリストの持ち物のラインナップから、その生活と人生を紐解いてみたい。
まずは彼の2021年時点の持ち物の全てを並べてみる。
electronics 3
1, iPhone
2, Bluetooth Earphone
3, Charging cable